孔子家語・原文
孔子謂子路曰:「君子而強氣,則不得其死;小人而強氣,則刑戮荐臻。《豳》詩曰:『殆天之未陰雨,徹彼桑土,綢繆牖戶,今汝下民,或敢侮余。』」孔子曰:「能治國家之如此,雖欲侮之,豈可得乎?周自后稷,積行累功,以有爵土,公劉重之以仁。及至大王亶甫,敦以德讓,其樹根置本,備豫遠矣。初,大王都豳,翟人侵之。事之以皮幣,不得免焉;事之以珠玉,不得免焉。於是屬耆老而告:『之所欲、吾土地。吾聞之,君子不以所養而害人。二三子何患乎無君?』遂獨與大姜去之,踰梁山,邑于岐山之下。豳人曰:『仁人之君,不可失也。』從之如歸市焉。天之與周,民之去殷,久矣。若此而不能天下,未之有也。武庚惡能侮?《鄁》詩曰:『執轡如組,兩驂如儛。』」孔子曰:「為此詩者,其知政乎?夫為組者,總紕於此,成文於彼;言其動於近、行於遠也。執此法以御民,豈不化乎?竿旄之忠告、至矣哉!」
孔子家語・書き下し
孔子子路に謂いて曰く、「君子にし而氣強からば、則ち其の死を得不。小人にし而氣強からば、則ち刑戮荐りに臻る。豳の詩に曰く、『天之未だ陰雨さざるに殆んで、彼の桑土を徹りて、牖戶を綢い繆る。今汝下民、敢えて余を侮る或るか』と」と。孔子曰く、「能く國家を治むる之此くの如からば、之を侮らんと欲すと雖も、豈に得可き乎。周は后稷自り、行いを積み功を累ね、以て爵土を有ち、公劉之に重ねるに仁を以う。大王亶甫に至るに及び、敦く德を以て讓り、其の根を樹て本を置き、豫めに備えること遠き矣。初め大王豳に都するや、翟人之を侵す。之に事えるに皮幣を以うるも、免がるるを得不り焉。之に事えるに珠玉を以うるも、免がるるを得不り焉。是に於いて耆老を屬め而之に告ぐ。『欲する所は吾が土地なり。吾れ之を聞く、君子養う所を以てし而人を害せ不と。二三子、何ぞ君無き乎患えん』と。遂に獨り大姜與之を去り、梁山を踰え、岐山之下于邑り。豳人曰く、『仁人之君、失う可から不る也』と。之に從うこと市に歸するが如き焉。天之周に與し、民之殷を去るや久しき矣。此くの若くし而天下に能え不るは、未だ之れ有らざる也。武庚惡んぞ能く侮らんや。鄁の詩に曰く、『轡を執ること組むが如く、兩つの驂儛うが如し』と」と。孔子曰く、「此の詩を為rえる者は、其れ政を知る乎。夫れ組を為くる者は、紕を此於總べ、文を彼於成す。其の近き於動きて、遠く於行わるるを言う也。此の法を執りて以て民を御うらば、豈に化まら不らん乎。竿旄之忠告は至れ矣哉」と。
孔子家語・現代語訳

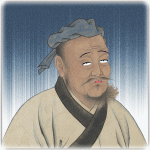
孔子が子路に言った。「君子は自己主張が激しいと、ろくな死に方をしない。つまらぬ人間でも自己主張が激しいと、しょっちゅう捕らえられ罰を受けるはめになる。だから豳の詩に言うのだ。”雨がまだ降らないうちに、桑の根を取って巣の出入り口を繕う。これでひどい目に遭うのを防げるだろうか”と。(何事も用心が肝心であるぞ。)」
孔子が言った。「このようにうまく治まった国家に、嫌がらせをするすきがどこにあろうか。周は開祖・后稷の時代から、よく働いて成果を出し、地位と領地を保ったが、公劉の時代になってからは、思いやりで領地をまとめることを始めた。
大王亶甫の時代になると、力を持ちながらへりくだることで、その国力を強化した。そうやって国の土台を固め、遠い未来に備えたのだ。はじめ大王は豳に都を置いたが、しょっちゅう北の蛮族に攻められた。連中は革や絹をやっても、玉をやってもおとなしくならなかった。
そこで大王は土地の長老たちを集めて相談した。”奴らが欲しいのは土地だ。ひとかどの人間なら、土地にこだわって人を傷付けないと私は聞いている。だから私は出て行くが、諸君は領主がいなくても気に病むな”と。そのまま妻の大姜を伴って行ってしまった。
そして梁山を越え、岐山のふもとに都を移した。豳の人が言った。”情け深い殿様じゃあ。失ってなるものか”と。そういうわけでぞろぞろと、市場に行くようにあとに従った。このようないきさつで、天は周に味方し、民は殷を見限って周についたが、この様子は長いこと続いた。
こうまで天下を思いのままにした国は、それまで一つもなかったのだ。だから周王朝成立後、一度は降った殷の一族・武庚も、やすやすとは反乱を起こせなかったのだ。例えるなら鄁の詩に言う通り。”組むように手綱を操り、両脇の馬は舞うようだ”と。」
孔子が言った。「この歌を作った者は、政治を知っていたんだろうな。そもそも組み紐というものは、手元で編むが模様が出来るのは紐の先だ。つまり近いところで仕事を積み重ねて、遠くに成果が現れるさまを言ったのだ。
こうした地道な取り組みに励むなら、民の生活を改善できないはずがない。”組み紐を組むように、四頭の馬を巧みに操る”。そう歌った竿旄の詩が与える教訓は、大したものと言わずばなるまい。」
孔子家語・訳注
豳詩:『詩経』豳風・鴟鴞(フクロウ)の歌を指す。
鴟鴞鴟鴞、既取我子、無毀我室。
鴟鴞よ鴟鴞、既に我が子を取れるに、我が室を毀つ無かれ。
恩斯勤斯、鬻子之閔斯。
斯く恩み斯く勤める、鬻な子之斯く閔む。
迨天之未陰雨、徹彼桑土、綢繆牖戶。
天之未だ陰雨せざるに迨んで、彼の桑土を徹りて、牖戶を綢い繆る。
今女下民、或敢侮予。
今女下民、敢えて予を侮る或るか。
予手拮据、予所捋荼、予所蓄租、予口卒瘏、曰予未有室家
予が手は拮め据み、予が所は荼を捋み、予が所は租を蓄め、予が口は卒に瘏むも、予れ未だ室家有らずと曰う。
予羽譙譙、予尾翛翛、予室翹翹、風雨所漂搖、予維音嘵嘵。
予が羽は譙譙れ、予が尾は翛翛れ、予が室は翹翹うく、風雨の漂い搖らす所、予れ維だ嘵嘵れ音く。
フクロウよフクロウ、すでに我が子を取ったのに、重ねて我が巣を壊すな。
深く深く愛した我が子が、実に哀れではないか。
今にも雨が降りそうな時、遠くの桑の根をついばんで、巣の窓や戸を繕った。
さあ下民ども、これでも私を侮るか。
私の手は縮みかがみ、私の巣には茅を集め、藁を集め、くちばしもおかしくなってしまったが、まだ巣は出来上がらない。
羽は破れ、尾も破れ、巣は危うく、風や雨に振り回される。私は恐れて鳴くしかない。
肉食のフクロウに我が子を取られた、弱い鳥のなげきの歌だが、「毛序・朱子ともに周公が国家経営の苦労をのべたものとする」と、中国古典文学大系『詩経』の注にある。
后稷:周王室の開祖。
公劉:后稷のひ孫。
大王亶甫:周文王の祖父。「古公亶甫」ともいう。
敦以德(徳)讓:逐語訳すると、”ねんごろに能力を用いてそれでへりくだる”。論語泰伯篇20に言う、「天下を三分してその二を有ち、以て殷に服い事う」と同じ事を言っているのだろう。腰の低い実力者に人望が集まるのは、古今東西変わらない。
なお「徳」とは徹頭徹尾”能力”のこと。道徳や人徳を意味しない。
豳:今の陝西省彬県。
翟人:北方の異民族。狄人と同じ。
皮幣:皮革と絹布。
耆老:長老。
大姜:大王亶甫の妻で、文王の祖母。
梁山:今の陝西省乾県の西北にある山。
岐山:今の陝西省東北部にある山。
武庚:殷最後の王・紂王(帝辛)の子で、一旦周に降ったが、のち周王室の反周公派と組んで反乱を起こした。
鄁:邶とも書く。もと殷の紂王が都を置いた地域の北部で、今の河南省湯陰県付近。ただし「執轡如組,兩驂如儛」の歌は『詩経』邶風・簡兮に「執轡如組」の句が見えるだけで、鄭風・大叔于田の詩に、この二つの句が記されている。
大叔于田は、鄭の荘公の弟で、母親に偏愛されて荘公と並ぶ権力を鄭国内で握り、ついに反乱を起こした共叔段が、狩りに出かける様を歌った歌。この反乱を乗り切ったことで、荘公は「小覇」と呼ばれる、鄭の黄金時代を築き上げた。
叔于田、乘乘馬、執轡如組、兩驂如舞。
叔の田于は、乘馬を乘り、轡を執ること組むが如く、兩つの驂舞うが如し。
叔在藪、火烈具舉。襢裼暴虎、獻于公所。
叔藪に在り、火烈く具に舉がる。襢ぎ裼ぎて虎を暴ち、公の所于獻る。
將叔無狃、戒其傷女。
將に叔よ狃れる無かれ、其れ女を傷めるを戒む。
共叔段が狩りに出る、その四頭立ての引き馬のさま、手綱を取ること組むがごとく、両脇の馬は舞うようだ。
共叔段が狩り場に着いた、獣を追う火が高々と上がる。もろ肌脱いで虎と組み討ち、殿様のもとへ差し上げる。
だが共叔段よ油断するな、災いがその身に降りかからぬように。
竿旄:『詩経』鄘風・干旄の歌を指す。
孑孑干旄、在浚之郊。 素絲紕之、良馬四之。 彼姝者子、何以畀之。
孑孑たる干旄は、浚之郊に在り。 素絲之を紕み、良き馬之れ四なり。 彼の姝き者の子、何以て之に畀えん。
牛の尾の差し物が一本、浚(鄭国のまち)のまちの郊外にさしかかる。白糸を組むように、よい馬四頭を走らせる。さて麗しのあの人に、一体何を贈ろうか。
孔子家語・付記
「君子にして気強からば…」で始まるお説教の聞き手に、一門きっての武人とされる子路を持ってきたのは、いかにも出来過ぎており、話が史実としても聞き手は子路だけではなかろう。詩についてのウンチク語りは今日的にはうんざりだが、孔子在世当時必須の教養だったからだ。