孔子家語・原文
1
孔子為*魯司寇,斷獄訟,皆進眾議者而問之,曰:「子以為奚若?某以為何若?」皆曰云云。如是,然後夫子曰:「當從某子幾是。」
*和刻本により謂→為。
2
孔子問漆雕憑曰:「子事臧文仲、武仲,及孺子容,此三大夫孰賢?」對曰:「臧氏家有守龜焉,名曰蔡。文仲三年而為一兆,武仲三年而為二兆,孺子容三年而為三兆,憑從此見之*。若問三人之賢與不賢,所未敢識也。」孔子曰:「君子哉,漆雕氏之子!其言人之美也,隱而顯;言人之過也,微而著;智而不能及,明而不能見。孰克如此?」
*和刻本により之見→見之。
3
魯公索氏將祭而亡其牲。孔子聞之,曰:「公索氏不及二年將亡。」後一年而亡。門人問曰:「昔公索氏亡其祭牲,而夫子知其將亡,何也?」曰:「夫祭者,孝子所以自盡於其親。將祭而亡其牲,則其餘所亡者多矣。若此而不亡者,未之有也。」
孔子家語・書き下し
1
孔子魯の司寇為りて、獄訟を斷むるに、皆な眾ろの議る者を進め而之に問う。曰く、「子は以て奚若と為すか。某は以て何若と為すか」と。皆な云云と曰う。是の如くして、然る後に夫子曰く、「當に某子の是れ幾きに從わん」と。
2
孔子漆雕憑に問うて曰く、「子は臧文仲、武仲,及孺子容に事えたり。此の三大夫、孰か賢しきか」と。對えて曰く、「臧氏は家に守る龜有り焉、名づけて蔡と曰う。文仲三年にし而一たび兆いを為し、武仲三年にし而二たび兆いを為し、孺子容は三年にし而三たび兆いを為せり。憑此從り之を見れば、三人之賢與不賢とを問うは、未だ敢えて識らざる所の若き也」と。孔子曰く、「君子なる哉,漆雕氏之子。其の人之美を言う也、隱し而顯わる。人之過ちを言う也、微かにし而著わす。智にし而及ぶ能わ不、明にし而見る能わ不。孰か克く此の如からん」と。
3
魯の公索氏、將に祭らんとし而其の牲を亡う。孔子之を聞きて曰く、「公索氏、二年に及ば不して將に亡びん」と。一年後れ而亡べり。門人問うて曰く、「昔公索氏其の祭の牲を亡えるに、し而夫子其の將に亡ばんとするを知るは、何ゆえ也」と。曰く、「夫れ祭者、孝子所以自ら其の親於盡すを以いる所なり。將に祭らんとし而其の牲を亡えるは、則ち其の餘り、亡える所者多き矣。若し此し而亡び不る者、未だ之れ有らざる也。」
孔子家語・現代語訳
1
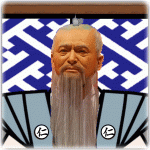
孔子が魯国の最高法官になった。刑事裁判の判決を下すに当たっては、いつも陪審員を呼んで意見を聞いた。「あなたはどう思われるか? こなたはどう思われるか?」と。みなしかじかと答えた。
こうした根回しを終えたあとで、孔子は言った。「なにがし殿の意見がほぼ正しいですから、それに従いましょう。」
2
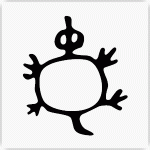
孔子が漆雕憑に質問して言った。「あなたは臧文仲・武仲、そして孺子容に仕えましたが、このお三方のうち、誰が偉かったですか。」
その答え「臧氏は家に亀の甲羅を仕舞い込んでおり、その甲羅を蔡と名付けていました。文仲は三年に一度、その甲羅を焼いて占い、武仲は二度、孺子容は三度占いました。私はこのことを思いますと、三人の誰が偉かったなどということは、とても分かりません。」
孔子「まことにご立派な君子でござるなあ、漆雕氏の若様よ。人の長所を言う時には、隠すように言ってもその実はっきり誉め、短所を言う時には、くらますように言ってもその実はっきり指摘した。知的だが不出来の振りをし、明察だが見えない振りをする。誰にも真似の出来ないことでござる。」
3
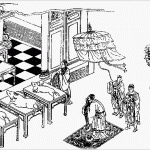
魯の公索氏が祖先の祭を行おうとしたところ、いけにえの獣を逃がしてしまった。孔子が話を聞いて言った。「公索氏は二年もしないうちに滅びるぞ。」はたして一年後に滅んでしまった。
門人が孔子に問うた。「以前公索氏はいけにえを逃がし、先生は滅亡を予知なさいました。どうしておわかりになったのですか?」
孔子「そもそも祖先の祭というものは、孝行者が自分の誠意の限りを尽くして執り行うものだ。いけにえを逃がしてしまうような不心得者は、それ以外の点でも誠実さに欠く点がきっとあるものだ。そういう不孝者が滅ばなかったことは、未だかつてないものだ。」
孔子家語・訳注
1
司寇:裁判官。『史記』の記述では、孔子は魯国の「大司冦」になったとされている。
斷(断)獄訟:刑事事件に判決を下す。
進:高い地位に昇らせる。ここでは、呼び集めて尊重すること。
奚若・何若(いかん):漢文の「いかん」については、孔子家語三恕3の語釈を参照。
幾:近い。
2
漆雕憑:孔子の弟子、漆雕開(→論語公冶長篇5)の縁者か、と古来言われる。まるで記録が無いから、そうとしか言いようが無いのだ。
孔子の「漆雕氏之子」という言い廻しは若者に対するもので、しかも「子」と呼びかけている。若いが孔子より身分が高かったのだろう。
ただし元ネタの『説苑』では、「漆雕馬人對曰」となっており、「漆雕人を馬りて對えて曰く」と読む。すると「憑」は人名ではないことになるが、事実は古代の闇の中で、もう誰にも分からない。
臧文仲・武仲:魯国の家老。文仲は武仲の父で、孔子誕生より70年ほど前に没した魯の大夫(→論語衛霊公篇14)。武仲は孔子が生まれた頃までに活躍した、魯の重臣。政争に敗れて亡命した(→論語憲問篇15)。
孺子容:臧武仲の跡継ぎかと古来言われる。これもまた、そうとしか言いようが無い。孺子とは”若者”の意。
守龜(亀):占いに用いる亀の甲羅を、大事に保管すること(→論語公冶長篇17)。
兆:占う。原義は、占うに際し、亀の甲や鹿の肩甲骨をあぶるとひび割れが出来るが、その象形。

智而不能及・明而不能見:ここでの「而」を「ごとし」と読み出して、”知的でありながら出来ないように振る舞い、洞察力がありながら見えないように振る舞った”と訳す本もある。『大漢和辞典』にも記載。しかし漢文読解の側から見ると、こんな珍義に一々付き合ってられない。
『学研漢和大字典』に言うように、「しかも」「しかるに」「しかれども」とよみ、「~ではあるが」「しかし」「それなのに」「~であっても」と訳す、と捉えた方が精神衛生上よろしい。
3
公索氏:この『孔子家語』と元ネタの『説苑』にしか出てこない姓で、詳細は分からない。
亡:ここでは犠牲獣を”逃がした”意の他に、公索氏が”亡”した、と書かれている。公索氏の当主が死去したと考えてもいいし、公索氏の一族が滅んだと考えてもいい。この漢字一文字だけでは、いずれとも決めかねる。
牲:いけにえの獣。春秋戦国時代の祭とは血なまぐさいもので、いけにえを文字通り血祭りにあげて祀った。それらのいけにえは祖先や神霊へのお供えであり、あの世の食物でもあった。だからこうしたお供えを「血食」という。
孔子家語・付記
1は『説苑』至公篇のコピペ。
2・3は『説苑』権謀篇のコピペ。