孔子家語・原文
1
虞、芮二國爭田而訟,連年不決。乃相謂曰:「西伯、仁人也。盍往質之。」入其境,則耕者讓畔,行者讓路;入其邑,男女異路,斑白不提挈;入其朝,士讓為大夫,大夫讓為卿。虞、芮之君曰:「嘻!吾儕小人也,不可以履君子之庭。」遂自相與而退,咸以所爭之田為閑田矣。孔子曰:「以此觀之,文王之道,其不可加焉!不令而從,不教而聽。至矣哉!」
2
曾子曰:「狎甚則相簡,莊甚則不親。是故君子之狎足以交歡,其莊足以成禮。」孔子聞斯言也,曰:「二三子志之!孰為參也不知禮也?」
3
哀公問曰:「紳委章甫,有益於仁乎?」孔子作色而對曰:「君胡然焉!衰麻苴杖者,志不存乎樂,非耳弗聞,服使然也;黼紱袞冕者,容不褻慢,非性矜莊,服使然也;介冑執戈者,無退惴之氣,非體純猛,服使然也。且臣聞之,好肆不守折,而長者不為市,竊夫其有益與無益,君子所以知。」
孔子家語・書き下し
1
虞、芮二國田を爭い而訟うに、連年決まら不。乃ち相い謂いて曰く、「西伯は仁の人也。盍ぞ往きて之に質さざる」と。其の境に入るに、則ち耕す者は畔を讓り、行く者は路を讓る。其の邑に入るに、男女路を異え、斑ら白は提げ挈げ不。其の朝に入るに、士は大夫の為に讓り、大夫は卿の為に讓る。虞、芮之君曰く、「嘻、吾が儕は小人也。以て君子之庭を履む可から不」と。遂に自ら相い與にし而退き、咸な爭う所之田を以て閑み田と為せる矣。孔子曰く、「此を以て之を觀れば、文王之道は、其れ加うる可から不り焉。令ら不し而從い、教え不し而聽く。至れる矣る哉」と。
2
曾子曰く、「狎るること甚しからば、則ち相い簡る。莊んなること甚しからば、則ち親しま不。是れ故に、君子之狎るるは足りて以て歡びを交え、其の莊んなるは足りて以て禮を成す」と。孔子斯の言を聞く也、曰く、「二三子之を志え。孰か參也禮を知ら不と為さん也」と。
3
哀公問うて曰く、「紳、委、章甫は、仁於益す有る乎」と。孔子色を作し而對えて曰く、「君胡ぞ然れ焉。衰麻、苴杖の者は、志い樂乎存ら不るも、耳の聞こえ弗るに非ず、服の然ら使める也。黼紱・袞冕の者は、容ち褻りに慢ろなら不るは、性の矜り莊んなるに非ず、服の然ら使める也。介冑に戈執る者は、退き惴ける之氣無きは、體の純ら猛けるに非ず、服の然ら使める也。且つ臣之を聞けり、肆を好まば折いを守ら不、し而長者は市を為さ不。夫れ其の益有る與益無きを竊むは、君子の以て知る所なり」と。
孔子家語・現代語訳
1
虞、芮二国が耕地を争い、何年たっても決着が付かなかった。そこで相談して言った。「西伯さまは最高の人格者だ。さあ、行ってどちらが正しいか決めて頂こう。」
西伯の領地に入ると、百姓は互いに耕地の境を譲り、道行く者は道を譲っていた。まちに入ると男女は別れて歩き、老人で重い荷物を持った者はいなかった。朝廷に入ると、士族は家老格にへりくだり、家老格は執政格にへりくだっていた。
虞、芮の国君「ああ、我らはつまらぬ人間だった。君子様のおられる朝廷に足を踏み入れると罰が当たる。」そう言って帰国し、争っていた耕地は、全て休耕地とした。
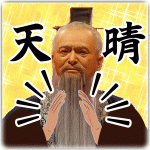
孔子「ここからして、西伯=文王の政治は全くつけ加えることがない完璧なものだ。命令しなくても従われ、教えなくても聞き入れられた。まったく立派なものだよ。」
2

曽子が行った。「親しくし過ぎれば互いに見くびるようになるし、態度を繕い過ぎれば親しめない。だから君子たる者、どんなに親しくしても、喜びを分かち合う程度に止め、態度をつくろうにしても、作法の見栄えを整える程度に止めるのだ。」
孔子がこの言葉を聞いて言った。「弟子の諸君や、よく覚えておきなさい。これで曽子が礼儀知らずだと言うものは、いなくなるだろうよ。」
3


哀公が孔子に問うた。「人前で身なりを整えるのは、何か利益があるのか。」孔子は真っ赤になって説教を始めた。「殿、なんとバカなことを仰せになる!」
「…喪服を着た者は、音楽を楽しもうとは思いませんが、耳が聞こえないのではなく、喪服がそうさせるのです。礼服を着た者は、いかにもどっしりして見えますが、人柄がそうなのではなく、礼服がそうさせるのです。鎧兜を身につけた者は、怖じ気づいた様子がありませんが、体が勇んでいるのではなく、武装がそうさせるのです。
加えて私はこういう話を聞いております。商売を好む者は、損ばかり続けることは出来ない、そもそも人格者は商売には手を出さない、と。利益があるかないかを、はじめからはっきり知っている、そうでなくては君子ではなく、ただのバクチ打ちに過ぎませんぞ。」
孔子家語・訳注
1
虞、芮:現在の山西省にあったとされる小国。
西伯:周の初代武王の父、文王。

盍:「なんぞ~ざる」。どうして~しないのか。ぜひ~しよう。
畔:「あぜ」と読み、耕地の境界。
斑白:ごま塩頭の老人。
提挈:手でぶら下げる。(要らぬ)荷物を持つ。
儕:ともがら。同列に並ぶ人々。
2
曾子:孔子の弟子で、現伝儒教の祖師の一人、曽参子輿のこと。
足以交歡(歓):「足以成禮」同様、伝統的には「以て歓を交うるに足り」と読むが、”それで喜び合うのに十分だ”の意味にしかならない。つまり文意が通じない。
3
哀公:孔子晩年の魯国の君主。
紳委章甫:紳は礼服の大帯、委は端委と同じく、礼服。章甫はかんむり。

有益於仁乎:ここでの仁は、”ひと”と解さないと文意が取れない。
衰麻:麻で作った喪服。

苴杖:喪中に用いる黒い竹の杖。「故人に死なれて私はこんなに悲しみ、歩行もままならないほど痩せ衰えています」という見せ物を演出するための小道具の一つ。
黼紱袞冕:黼紱は礼装用の前掛け。袞冕は龍の縫い取りのある礼服とすだれの付いた冠。合わせて、一番の礼装を言う。

介:よろい。
折:損をする。
長者:人格者。
竊:”明らかにする”の語義を『大漢和辞典』に載せる。「且臣聞之」以下は、『孔子家語』の創作者だった王粛も解釈を半ば放り出し、江戸の太宰春台も意味不明としたらしい。
孔子家語・付記
1は『説苑』君道篇の、2は説叢篇のコピペ。3は『荀子』哀公篇のコピペ。