孔子家語・原文
1
孔子之郯,遭程子於塗,傾蓋而語終日,甚相親。顧謂子路曰:「取束帛以贈先生。」子路屑然對曰:「由聞之,士不中閒見,女嫁無媒,君子不以交,禮也。」有閒,又顧謂子路,子路又對如初。孔子曰:「由!《詩》不云乎?『有美一人,清揚宛兮,邂逅相遇,適我願兮。』今程子,天下賢士也。於斯不贈,則終身弗能見也。小子行之。」
2

孔子自衛反魯,息駕於河梁而觀焉。有懸水三十仞,圜流九十里,魚鱉不能道,黿鼉不能居。有一丈夫,方將厲之。孔子使人竝涯止之,曰:「此懸水三十仞,圜流九十里,魚鱉、黿鼉不能居也,意者難可濟也。」丈夫不以措意,遂度而出。孔子問之曰:「子巧乎?有道術乎?所以能入而出者何也?」丈夫對曰:「始吾之入也,先以忠信;及吾之出也,又從以忠信。措吾軀於波流,而吾不敢以用私,所以能入而復出也。」孔子謂弟子曰:「二三子識之!水且猶可以忠信成身親之,而況於人乎?」
孔子家語・書き下し
1
孔子郯に之き、塗於程子に遭う。蓋を傾け而語ること終日、甚だ相い親む。顧みて子路に謂いて曰く、「束なす帛を取りて以て先生に贈れ。」子路屑然に對えて曰く、「由や之を聞けり、士は閒見るに中ら不、女の嫁ぎて媒無きは、君子交るを以て不ざるが、禮也と。」閒有りて、又た顧みて子路に謂うも、子路又た對うること初めの如し。孔子曰く、「由や、詩に云わ不乎、美一人有り、清げに揚し宛なる兮、邂い逅いて相い遇う、我が願いに適える兮、と。今や程子は、天下の賢士也。斯於贈ら不らば、則ち身を終えるも見る能わ弗る也。小子之を行れ」と。
2
孔子衛自り魯に反り、河梁於駕を息め而觀た焉。懸水有りて三十仞,圜り流るること九十里,魚鱉道る能わ不、黿鼉居る能わ不。一丈夫有りて、方に將に之を厲らんとす。孔子人を使て涯に竝びて之を止めしめて曰く、「此の懸水三十仞、圜り流るること九十里、魚鱉、黿鼉だに居る能わ不る也、意う者濟る可くは難き也」と。丈夫意を措くを以てせ不、遂に度り而出づ。孔子之を問うに曰く、「子の巧みなる乎。道術有らん乎。能く入り而出づる者の所以は何なる也」と。丈夫對えて曰く、「始め吾之入る也、先づ忠信を以う。吾之出づるに及ぶ也、又た忠信を以いるに從う。吾が軀を波なす流れ於措くも、而て吾敢えて私を用いるを以てせ不るは、能く入り而復た出づる所以也」と。孔子弟子に謂いて曰く、「二三子之を識れ。水且つ猶お忠信を以て身之に親しむを成す可し、而た況んや人於乎」と。
孔子家語・現代語訳
1
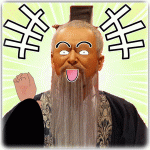
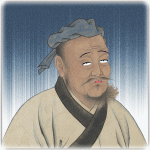
孔子が郯国に出かける途中、程子とたまたま出会った。甚だ意気投合して、互いに車の端に寄りかかって一日中語ったために、車の天蓋は傾きっぱなしだった。
孔子はお供の子路の方を向いて言った。「絹を一束、このお方に差し上げなさい。」子路がすぐさま言い返した。「私はこういう話を聞いています。ひとかどのサムライには、めったに出会えるものではない。こんな野面で行き会っただけの人は、仲人無しで嫁いだアバズレ女と同じです。そんな者とは付き合わないのが君子の常識だ、と。」
しばらく間を置いて、孔子がまた子路に言いつけたが、同じように答えた。そこで孔子は言った。「子路よ、詩に言うではないか。可愛いあの子の目元うるわし、会えてうれしや、思いが叶った、と。この程子どのは、天下の賢者であられる。今ここで記念の品を差し上げないようでは、生涯二度と会えないお方じゃ。さあ子路や、差し上げるのじゃ。」
2
孔子が衛から魯に帰国する途上、河に架かった橋のたもとに車を止めて見れば、三十仞もある滝が落ち、そこから激流が九十里も続いている。あまりに急なので、魚やスッポンも泳げない。大ガメもワニも住み着かない。
ところが男が一人、今まさにこの流れを渡ろうとしている。孔子はお供を何人も岸にやって、こう言わせた。「この滝は三十仞、流れは九十里。魚やスッポン、大ガメやワニでさえかなわない。どう考えても渡るのは無理です、おやめなされ」と。
ところが男は思い切りよく、とうとう渡り切って流れから上がった。孔子が男に問うた。「なんとも優れた泳ぎでござる。何か不思議な法を心得てござるか? こんな流れに飛び込んで、上がって来られる法とは何でござるか?」と。
男が答えた。「流れに入るも出るも、ひとえに嘘偽りの無い真心です。さかまく流れに身を投げようとも、我が身のことをいささかも思わないことが、こんな流れに出入りするコツです」と。
孔子が弟子たちに言った。「諸君、今のお話を覚えておきなさい。水ですら、真心が通じて親しめるのじゃ。人ならなおさらじゃぞ」と。
孔子家語・訳注
1
郯:春秋時代の国名。孔子17歳の時、魯に来た郯国公から、有職故実を教わったという伝説がある。
程子:春秋時代の人名。程本とも呼ばれる。道家の一人に数えられる。晋国出身で博識で知られ、趙簡子が招いたが応じなかった。斉に遊説して晏嬰の客となり、子華子と名乗った。同名の書は程子の著作だとされたが、漢代には失われ、現伝の書は宋代の偽作であると考証されている。
傾蓋:互いに親しむことの形容。
先生:現代中国語と同様、”このお方”・”~さん”という敬称。読み下しとしては「せんじょう」と読みたいところだが、訳者の趣味に過ぎない。
屑然:多くの漢和辞典では、本章または元ネタである『説苑』などを引いて”突然”の意味だとする。
閒見:次々に現れること。閒=間として、「間々見る」と読めば分かった気になれる。
女嫁~禮也:直訳すると、”仲人無しで結婚したような女とは、君子は付き合わないのが礼法だ”。この前後の文脈は、原文にはっきりと書かれていないので、どうとでも読める。「コレコレこのように解釈せねばならぬ」と言い出した元の儒者にも、論拠はない。
つまり権威に従って読むのが無難で儲かるから、日中の儒者と大学教授はそう読んできたのだが、訳者が今さら権威に従ったところで、一銭の収益も無いから従わない。それより「こう読んだ方が理屈に合う」との考えに従うが、それも訳者の趣味に過ぎない。
禮也:”それが礼法にかなっている”。
禮(礼)とは君子の立ち居振る舞い一切を規定するお作法集であり、君子認定基準でもある。孔子没後のメシの種&帝国儒教では、つまり外からはめられるカタであり、ワクでもある。従って自発的な、善意ある”良識”ではなく、欲得のために従わざるを得ない”常識”と訳した。
参考:論語における「禮(礼)」
有美~願兮:『詩経』鄭風・野有蔓草の一節。野辺の逢瀬を喜ぶ歌で、おそらくは”仲人無し”を掛けている。ただし帝国儒教的観点からは、孔子が鄭の歌を「淫らだ」だと言って嫌った(論語衛霊公篇11)という公式見解と、本章とがどう整合するのかフシンである。
宛:からだを丸くかがめて、なよなよとしたさま。もう一つ、”あたかも”という意味が漢字にはある。日本古語の「えん(艶)なり」は前者の意味だが、「あてなり」はもと”あたかも”の意であったはずが、”なまめかしい”の意になったのは漢字「宛」に引っ張られたため。
手紙などの「宛」になると、完全に日本語だけの語義になる。
揚:『大漢和辞典』に『詩経』を引いて”眉目のあたりがひろくうるわしい”と語釈がある。ひたいが広いことは、美人の条件の一つとされたようだ。
2
仞:周代の一仞は七尺、一尺は約22.5cm。三十仞は約47.25mとなる勘定。
里:周~漢の一里は約400m。九十里で約36kmとなる勘定。
いずれにせよ「仞」同様、まじめに数値を記した話ではなく、適当に多そうな数値を三倍順で記したに過ぎない。儒者に限らず中国の知識人は、過去も現在も利益にはことのほか敏感だが、実測値には全く無関心だから、まじめに訳そうとすればするほど、頭がおかしくなる。
「中国の経済統計が当てにならない」のは、少なくとも春秋時代以降ずっとそうなのだ。都合のよい主観を客観に転化する厳しさに生きている。数理に無関心な数千年を過ごしながら、古代文明の中唯一生き延びた中華文明の面白さは、むしろこうした矛盾を知ることにある。
魚鱉:魚とスッポン。漢文では小型の水棲生物一般をそう呼ぶことがある。
黿鼉:アオウミガメとワニ。ただし河にウミガメがいるわけはないので、ただ”大きなカメとワニ”、つまり大型の水棲生物一般を意味しているに過ぎない。
厲:原義は”サソリの如く荒々しい砥石(で研ぐ)”だが、『大漢和辞典』に”着物をかかげて水を渡る”の語釈を載せる。
遂:「ついに」と読み下した場合、”そのまま・すぐに”の意と、”結果として・とうとう”の意がある。
忠信:まごころがあって嘘が無いこと。忠はお中の心で、自分を偽らないこと。信は人に対する言葉を守る事で、人を偽らないこと。
孔子家語・付記
1は『韓詩外伝』巻二・『説苑』尊賢篇の、2は『列子』説符篇のコピペ。
本章がいずれ作り話であることは言うまでも無いが、その理由の一つは道家との親和性。春秋から戦国にかけて、儒家は人と向き合うことには熱心だったが、自然と向き合うことには無関心だった。このため天変地異を相手にせざるを得ない政権は、道家もまた必要とした。
儒教が国教化された前漢時代も同様で、道家は帝室や重臣の間で一定の支持を得ており、本章を筆写した漢代の儒者たちも、さほどうるさく道家を毛嫌いしなかったのだろう。『列子』には孔子を馬鹿にした話も多いが、不世出の賢者として一定の敬意は払っている。
帝国儒教的に言えば、列子は孟子が非難した儒家の大敵であり、世を乱す馬鹿者どもの親分だったはず。ところが後漢末から三国時代の王粛は、この孔子家語をでっち上げるに、不倶戴天の列子を平気で持ち出した。儲かるなら悪魔とも取引するのが中国人の心得というものだ。
『列子』は、あるいは道家、あるいはどこまでも現実主義の思想としてこんにち紹介されるが、それでも本章と同じく、原典に河にいるはずの無い「黿」=アオウミガメと記す。
ヨーロッパでは、ギリシアの学者がサメを「海の犬」と呼んだため、中世には波間に浮かぶ犬の挿絵として、まじめな事典に描かれたという。事ほど左様に、事実を事実として記すのはむつかしい。現代の「意識高い人」同様、自然よりも人間をだます方が儲かりやすいからだ。
事情は儒家も『論語』も変わらない。麒麟を麒麟と判別できたように、孔子は同世代人の中では際立って博物に詳しかったが、自然に対して我意を通せるとは思っていなかった。それゆえ疫病に斃れた同志を、「これも天の定めなのか!」と恨みつつ諦めるしか無かった。
参考:論語雍也篇10
だから孔子は怪力乱臣を語れなかったのだ。語らなかったのではない。