孔子家語・原文
1
孔子將行,雨而無蓋。門人曰:「商也有之。」孔子曰:「商之為人也,甚恡於財。吾聞與人交,推其長者,違其短者,故能久也。」
2
子貢問於孔子曰:「死者有知乎?將無知乎?」子曰:「吾欲言死之有知,將恐孝子順孫妨生以送死;吾欲言死之無知,將恐不孝之子棄其親而不葬。賜欲知死者有知與無知,非今之急,後自知之。」
3
子貢問治民於孔子。子曰:「懍懍焉!若持腐索之扞馬。」子貢曰:「何其畏也?」孔子曰:「夫通達之御皆人也,以道導之,則吾畜也;不以道導之,則讎也。如之何其無畏也?」
4
魯國之法,魯人有贖臣妾於諸侯者,皆取金於府。子貢贖人於諸侯,而還其金。孔子聞之,曰:「賜失之矣!夫聖人之舉事也,可以移風易俗,而教導可以施於百姓,非獨適身之行也。今魯國富者寡而貧者眾,贖人,受金則為不廉,則何以相贖乎?自今以後,魯人不復贖人於諸侯。」
5
子路治蒲,見於孔子曰:「由願受教於夫子。」子曰:「蒲其何如?」對曰:「邑多壯士,又難治也。」子曰:「然。吾語爾,恭而敬,可以攝勇;寬而正,可以懷強;愛而恕,可以容困;溫而斷,可以抑姦。如此而正不難矣。」
孔子家語・書き下し
1
孔子將に行かんとして、雨ふり而蓋無し。門人曰く、「商也之を有てり」と。孔子曰く、「商之人と為り也、甚だ財於恡なり。吾れ聞くならく、人與交わるに、其の長けたる者推し、其の短者違らば、故に能く久しき也と。」
2
子貢孔子於問うて曰く、「死せる者は知有らん乎。將に知無からん乎」と。子曰く、「吾死之知有るを言わんと欲さば、將に孝子順孫の生を妨げて以て死を送るを恐る。吾死之知無きを言わんと欲さば、不孝之子の其の親を棄て而葬ら不るを恐る。賜の死せる者の知有る與知無きとを知らんと欲するは、今之急りに非ざれば、後に自ら之を知れ」と。
3
子貢民の治めを孔子於問う。子曰く、「懍懍み焉れ。腐れたる索を持ちて扞き馬を之るが若し」と。子貢曰く、「何ぞ其れ畏るる也」と。孔子曰く、「夫れ通じ達れるもの之皆な人を御する也、道を以て之を導かば、則ち吾が畜也。道を以て之を導びか不らば、則ち讎也。之を如何ぞ其れ畏るる無からん也」と。
4
魯國之法に、魯人の臣妾を諸侯於贖う者有らば、皆な府於金を取る。子貢人を諸侯於贖い而、其の金を還せり。孔子之を聞きて曰く、「賜や之を失える矣。夫れ聖人之事を舉ぐる也、以て風を移し俗を易う可し、し而教え導くは以て百姓於施す可し、獨り身に適う之行いに非る也。今魯國の富める者は寡くし而貧者は眾し、人を贖いて金を受くるを、則ち廉あら不ると為さば、則ち何を以てか相い贖わん乎。今自り以後、魯人復た人を諸侯於贖わ不らん。」
5
子路蒲を治めて、孔子於見えて曰く、「由や願わくば夫子於教えを受けん」と。子曰く、「蒲や其れ何如」と。對えて曰く、「邑に壯士多く、又た治め難き也」と。子曰く、「然り。吾れ爾に語らん。恭しくし而敬みあらば、以て勇を攝む可し。寬やかにし而正しからば、以て強を懷く可し。愛し而恕わば、以て困を容るる可し。溫かにし而斷からば、以て姦を抑うる可し。此の如くし而正さば、難しから不る矣。」
孔子家語・現代語訳
1


孔子が出かけようとすると、雨が降り出したが車の傘が無い。門人が言った。「子夏が傘を持っています。」孔子が言った。「子夏の性格は、たいそうけちん坊だ。私が聞いた話では、人との交わりは、相手の長所を伸ばし、短所に触らないようにするから、長持ちするのだと。子夏に借りるのは止めておこう。」
2
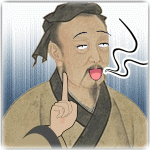

子貢が孔子に質問した。「死んだ人に知覚はあるんですかね。あるはずが無いんでしょうかね。」
先生が言った。「私が”死者に知覚はある”と言えば、世の孝行者や従順な孫が、そのうち自分の人生を台無しにしてまで、親や祖父母の葬儀を手厚くするだろう。それは困る。だが”死者に知覚なんて無い”と言えば、不孝者が親を放り出してまともな葬儀もやらなくなる。それも困る。
子貢よ、お前が死者の知覚の有る無しを知りたいのは、差し迫った事情からでは無い。だからおいおい、自分で知るんだな。」
3


子貢が民の統治を孔子に質問した。先生が言った。「とにかく慎重に行え。丁度腐った手綱を手に取って、気の荒い馬を進ませるように。」
子貢が言った。「何でそんなにビクビクせねばならんのです?」
孔子が言った。「政治の達人が大勢の人を治める際、原則通りに導くなら、すっかり自分の家畜のように手懐けられる。しかし無原則に政治を行うと、まるまる民衆が敵に回る。となるとだな、慎重にならざるを得んだろうが。」
4


(戦場での捕虜はもちろん、占領された土地の住民は、まるごと奴隷にされてしまう。)
魯国の法律では、魯国人が他国の殿様から、その奴隷の身柄を買い戻す場合、代金は政府から貰えることになっていた。ところが金持ちの子貢は、他国の殿様から人を買い戻したのに、受け取った代金を政府に返してしまった。
孔子がそれを聞いて言った。「子貢の奴はまずいことをやらかした。そもそも聖人が何かをするのは、民の風習や習慣を改善し、教育を民に施すためだ。自分一人がいい気になるためにやるんじゃない。
今魯国に金持ちは少なく、貧乏人は多い。身代金を政府に肩代わりして貰った者が、世間で税金泥棒呼ばわりされてしまうなら、大勢の貧者はどうやって、お互いの身柄を買い戻せばいいのか。これではこの先、魯国の者は他国の殿様から、人を買い戻そうとはしなくなるぞ。」
5
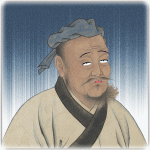

子路が蒲のまちの代官になった時、孔子に会って言った。「私めはどうか先生にお教え頂きたいと存じます。」
先生が言った。「蒲のまちはどうかね。」
応えて言った。「まちには鼻息の荒い者が多く、さらには言うことを聞きませんので、治めにくいです。」
先生が言った。「そうじゃろうな。じゃがお前にいい事を教えてやろう。
腰を低くして丁寧に接すれば、気の荒い連中でも言うことを聞かせることが出来る。取り締まりを緩やかにするが法は曲げずにおけば、強情な連中でも手懐けることが出来る。可愛がって同情してやれば、行き詰まった連中でもまちに置いてやれる。情け深いが決断ははっきりしているなら、悪だくみをする連中を押さえつけることが出来る。
このようにして民を躾けると、統治も難しくないだろうよ。」
孔子家語・訳注
1
蓋:車に差し掛ける天蓋。
商:孔子の弟子で孔門十哲の一人、卜商子夏のこと。
為人:ここではひととなり・性格。原義は”人の様子”。
恡:吝に同じ。けち。
違:避ける、離れる、食い違う。
2
將:”今にも~しようとする”という未来を表す場合が多いが、ここでは”きっと~だろう”・”~のはず”の意でも使われている。
賜:孔子の弟子で孔門十哲の一人、端木賜子貢のこと。
3
懍:おそれ謹む。慎重にする。稟の字の上部は、作物を仕舞い込む納屋を意味する。散漫な心を仕舞い込んで、ピリピリと謹むこと。
扞:原義は干=さすまたで攻撃を”防ぐ”だが、駻と音が通じて、馬など家畜の荒々しさを言う。

道:孔子在世当時の意味では、原則・やり方のこと。この話が創作された時代では、儒教の教えそのものを指すと考えてもいい。
畜:原義はむしろ、くさかんむりの付いた蓄の方で、貯えることだが、家畜とあまり区別されずに使われる。
讎:原義は”対等(な相手)”・”対等なお返し”。対等であることから対抗できる相手→かたきへと意味が派生した。
4
魯人:「ろひと」と読み下して”魯の国のひと”と解するのが漢文のお作法。
贖:あがなう。財貨で罪の埋め合わせをしたり、人身を買い戻すこと。
臣妾:男女の奴隷。
夫:そもそも。
聖人:孔子在世当時では”万能の人”を意味するが、後世では儒教的価値観にかなった、賢い人格者を意味するようになった。
可:四角四面に”~できる”の意だけ覚えていると、漢文が読めなくなる。日本古語の「べし」と同様、適当や勧誘、当然の語義がちゃんと辞書に載っている。
適身之行:身にかなった行い。
眾:衆の異体字。
廉:かどめ。けじめ。
5
子路:孔子の弟子で孔門十哲の一人、仲由子路のこと。
蒲:子路が代官を務めた、衛国のまち。
壯士:意気盛んな大人の男。
又:さらには。
攝:「摂」の正字体。原義は”とる”だが、ここでは枠の中にきちんとおさめること。
恕:相手を自分の「如く」思う「心」。同情してやること。
孔子家語・付記
1は『説苑』雑言篇のコピペ。ただし「商之為人也、甚短於財」(子夏の様子は、財産に困っている)となっており、子夏がけちん坊であるという話にはなっていない。貧しい弟子を思いやる、孔子の美談になっている。十の指に入る高弟だろうと、儒者の捏造から逃れ得ない。
いわんや史実をや。ただし車は貴族のステータスシンボルで、代価も維持費も高かったから、孔子ですら維持しかねた(論語衛霊公篇26)。貧乏な子夏が傘だけ持っていたというのは話がおかしい。ゆえに王粛がケチ話に書き換えたことに理解は出来る。
2は『説苑』弁物篇のコピペ。3・4は政理篇のコピペ。
4は『説苑』では「孔子可謂通於化矣。故老子曰、見小曰明。」(孔子は社会教育の法を説くべき人だ。だから老子が「かすかなことを見分けられるのが、本当の知力だ」と言ったのだ)が後ろにくっついている。ただ当時の魯国に、本当にそんな法律があったのだろうか。
中国史における奴隷について、訳者は知る所が少ないが、少なくとも漢帝国の時代まではいたことがはっきりしている。奴隷になる原因は、戦争で捕虜になる、罪を犯して身分を落とされるのが主で、他文化圏のような、債務奴隷の話は読んだことが無い。
原文には「相贖乎」(お互いに買い戻せるだろうか)とあるので、魯国人が他国の殿様によって奴隷化される、ということなのだろう。となると、戦時捕虜の買い戻しを意味するのではなかろうか。それならば、代金に国庫補助があるというのもうなずける気がする。
ただし「臣妾」とあるから、捕虜と言っても男性、つまりは出征兵士だけが対象になるのでは無いだろう。攻め取られたまちの住人が、老若男女かまわずまるまる奴隷に落とされるのは、古代中国でも変わらない。孔子の意識でも、領民は君主の財産にほかならなかった。
5は『説苑』政理篇の他、それに先行する『韓詩外伝』巻六にも載っている。