孔子家語・原文
1

孔子觀於魯桓公之廟,有欹器焉。夫子問於守廟者曰:「此謂何器?」對曰:「此蓋為宥坐之器。」孔子曰:「吾聞宥坐之器,虛則欹,中則正,滿則覆。明君以為至誡,故常置之於坐側。」顧謂弟子曰:「試注水焉。」乃注之水,中則正,滿則覆。夫子喟然歎曰:「嗚呼!夫物惡有滿而不覆哉!」子路進曰:「敢問持滿有道乎?」子曰:「聰明叡智,守之以愚;功被天下,守之以讓;勇力振世,守之以怯;富有四海,守之以謙。此所謂損之又損之之道也。」
2
孔子觀於東流之水,子貢問曰:「君子所見大水必觀焉,何也?」孔子對曰:「以其不息,且徧與諸生而不為也。夫水有似乎德,其流也,則卑下倨拘必循其理,此似義;浩浩乎無屈盡之期,此似道;流行赴百仞之谿而不懼,此似勇;至量必平之,此似法;盛而不求概,此似正;綽約微達,此似察;發源必東,此似志;以出以入,萬物就此化絜,此似善化也。水之德有若此,是故君子見必觀焉。」
孔子家語・書き下し
1
孔子魯於桓公之廟を觀るに、欹器有り焉り。夫子廟を守る者於問うて曰く、「此れ何の器と謂うや」と。對えて曰く、「此れ蓋し宥坐之器為らん」と。孔子曰く、「吾れ宥坐之器を聞くに、虛ならば則ち欹き、中らならば則ち正ち、滿つれば則ち覆える。明君以て誡めの至りと為し、故に常に之を坐る側於置くと」と。顧みて弟子に謂いて曰く、「試みに水を注ぎ焉れ」と。乃ち之に水を注ぎ、中らならば則ち正ち、滿つれば則ち覆える。夫子喟然として歎じて曰く、「嗚呼、夫れ物は惡んぞ滿つる有り而覆ら不る哉」と。子路進みて曰く、「敢えて問う、滿つるを持つに道有らん乎」と。子曰く、「聰明叡智、之を守るに愚を以う。功し天下に被かるるに、之を守るに讓りを以う。勇力世に振うに、之を守るに怯えを以う。富四海に有てるに、之を守るに謙りを以う。此れ所謂、之を損いて又た之を損う之道也。」
2
孔子東に流るる之水於觀るに、子貢問うて曰く、「君子の大水を見る所、必ず觀焉んは、何ぞ也」と。孔子對えて曰く、「其の息ま不る、且つ徧く諸生に與え而為さ不るを以てする也。夫れ水は德乎似たる有り。其の流るる也、則ち倨り拘わるを卑しみ下して必ず其の理に循う、此れ義しきに似たり。浩浩乎として屈盡る之期無し、此れ道に似たり。流れ行きて百仞之谿に赴き而懼れ不、此れ勇に似たり。量に至るも必ず之を平らぐ、此れ法に似たり。盛り而概を求め不、此れ正すに似たり。綽約くして微に達る、此れ察するに似たり。源を發して必ず東す、此れ志に似たり。以て出で以て入る、萬物此れに就きて絜しと化る、此れ善く化うるに似たる也。水之德は此の若き有り、是れ故に君子見て必ず觀焉ん。」
孔子家語・現代語訳
1
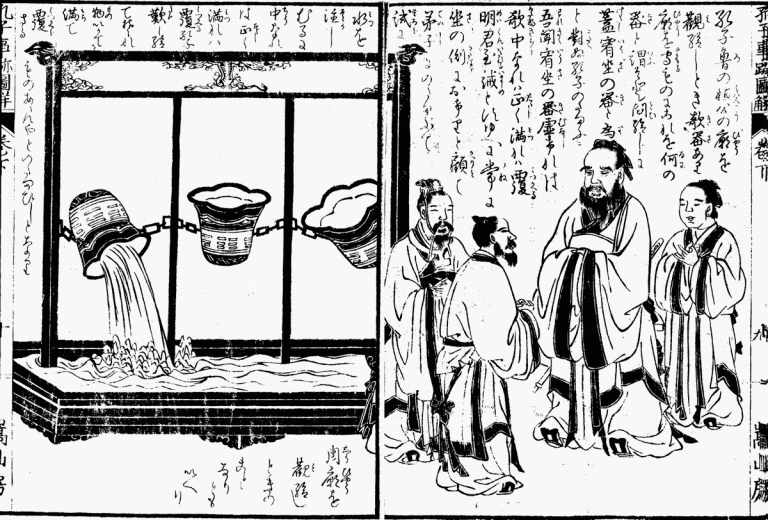
孔子が魯で桓公のみたまやを見物していると、傾いた器が吊ってある。先生がみたまやの番人に質問して言った。「これは一体何の器ですか。」応えて言った。「これはたぶん、我が身の心を戒める道具でしょう。」
孔子が言った。「私が心を戒める道具について聞いたところでは、空っぽの時は傾き、ほどほど入っていれば真っ直ぐに立ち、一杯になるとひっくり返ってしまう。名君たるものはそれを最高の戒めにしようとして、だからいつも座る場所の隣に置いておいたという。」
振り返って弟子に説明しながら言った。「というわけだから、試しに水を注ぎなさい、いっぱいになるまで。」それこれのやりとりがあった後、器に水を注ぐと、半分ほどの量なら真っ直ぐに立ち、いっぱいになるとどうあってもひっくり返ってしまった。
先生はため息をつきながら、思いを込めて言った。「ああ、そもそも万物は、満ち足りてしまえばどうしてひっくり返らない事があろうかのう。」そこへ子路が進み出て言った。「押して伺います。満ち足りたままでいられる法はあるでしょうか。」
先生が言った。「聡明で優れた智恵は、バカの振りをすることで守られる。天下が知るほどの功績は、譲ることで守られる。世間に轟く勇気は、おびえることで守られる。世界中こぞるほどの富は、へりくだることで守られる。これがいわゆる、卑下することで元を小さく見せる法、というものだ。」
2

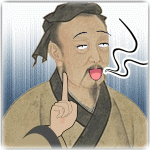
孔子が東に流れていく川を見渡している時に、子貢が質問して言った。「君子が大きな川を見る時、必ず思い比べる事とは、何でしょう。」
孔子が答えて言った。「その休み無く、そしてかたより無く万物を恵んでも、したり顔をしない事だな。
そもそも川は、隠然たる力に似ている。流れるに当たっては、必ず驕りやこだわりを捨てて、もののことわりに従う。これは究極の正しさに似ている。
広々として尽き果てる時も無いのは、この世の原則に似ている。流れ落ちて百仞の谷にいたろうとも恐れない、これは勇気に似ている。
かさが増えても減っても必ず平らかになる、これは法に似ている。盛り上がっても掻き落とす手間も無く自然に平らになる、これは物事を道理に近づける作用に似ている。
ゆったりと流れながら、隅々にまで行き渡る、これは深い洞察力に似ている。源流から始まって必ず東へと流れる、これは堅い意志に似ている。
水が物の間を出たり入ったりして、万物がその作用で綺麗になる、これは善へと導くのに似ている。
川の隠然たる力にはこのようなものがある。だからこそ、君子は川に出会って必ずそれを思い比べるのだ。」
孔子家語・訳注
1
觀(観):下記の通り、物事を揃えて見渡す・見比べることだが、ここでは、いろいろなものを見物する、の意。
魯桓公:?-BC694。孔子の生国・魯の君主。大変不名誉な伝説があり、隣国の斉から夫人(文姜)を迎えたが、これがとんでもないアバズレで、嫁ぐ前から実の兄、後の斉の襄公と密通していた。それを露知らぬ桓公は夫人にせがまれ、彼女を伴って襄公即位後の斉を訪れた。
待ち構えていた襄公は文姜を自分の宮殿に止めたまま出さない。文姜も出ない。さすがに不審に思った桓公が密通の証拠をつんだと知ると、襄公は怪力の公族に命じて桓公をひねり●させた。襄公は更に証拠隠滅を謀り、手を下した公族をも処刑した。桓公は背骨をへし折られた無残な姿だったというが、大国斉を相手に小国の魯は泣き寝入り。
ただし因果応報で、のち襄公は反乱に遭って●された。文姜の方は夫や兄の死後も生き延び、好き勝手な生活を送って天寿を全うしたという。
欹器:「欹」は傾く。以下のようなからくりの器とされる。
此謂何器:”これは何の働きをする器か”。同じ「いう」でも、「謂」はそれをめぐってあれこれ論評すること。ただ名前を問うたのでは無い。
宥坐之器:自分を戒めるための器、と古来解する。
試注水焉:試しにいっぱいまで水を注ぎなさい。「焉」は”~し終える”を意味し、ここでは”いっぱいまで”と訳した。この手の助辞を一つ覚えのように「置き字だ」といって無視している間は、仮に教授になれたにしても、いつまでたっても漢文が読めるようにならない。
乃:同じ「すなわち」でも、紆余曲折あってのち、の意。
喟然:ため息をつくさま。「喟」は「はぁ」と息を出すこと。
惡:悪い、憎む、の他に、「いずくんぞ」と読んで反語の語義を持つ。
損之又損之之道:減らすことで、さらに元を減らす方法。「又」は”さらに”。元ネタの『荀子』では、「挹而損之之道」(たもちてこれを損なうの道=維持するために減らすという方法)とあって文意がはっきりしている。
『孔子家語』が創作された三国・魏の学風は、編者である王粛と対立した何晏一派がもともと有力で、その学問は「玄学」と言われた。要するに、難解なウンチクをたれて物事を更に分からなくする学問、というか商売。なお「玄」には”てらう・ハッタリを掛ける”の意もある。
日本で言えば、戦時中自分から軍部のお先棒を担いだ西田幾多郎とその取り巻きが言い回った、絶対矛盾的自己同一論に似ている。西洋哲学に禅を混ぜ込んで作った、誰にも理解出来ず理解させるつもりも無い思想で、読経と同じくワケが分からない故のありがたさでしかない。


その衒学的(知識をひけらかす)な何晏一派を政争で打倒した王粛は、我が世の春を迎えたが、物事を難解にしたがる傾向は同じであり、このように原文をせっせと晦渋(文章などがむずかしくわかりにくいこと)にして書き換えている。まともな学者のすることではない。
2
觀(観):同じ「みる」でも、取りそろえて見比べること、見渡すこと、見て思い比べること。
屈盡:尽き果てる。
概:とかき。ますの中に穀物を入れて平らにならす棒。
綽約:ここではゆったりとしてしとやかなさま。また淖約に同じい場合、あでやか。めだって美しい。
微達:細かに隅々まで通じ達する。
孔子家語・付記
上記のように、1は『荀子』宥坐篇のコピペ。2も同様。両者共に、『韓詩外伝』『説苑』にも同じ話がある。
さて王粛を「まとも学者でない」と書いたが、中国では全ての行為は商売である。学者も金儲けの商売人であって、ワケわからない方が売れるとなれば、よろこんで分からなくするのが商売のコツというものだ。キタローはたまたま、同じ様な条件にあったに過ぎない。
こんにち漢文を読むのは、学業上押し付けられたのでなければ、中国や中国人とは何かを知るために他ならないが、世界の古代文明で唯一生き残っている中華文明とは、日本人の度肝を抜くほど、その想像を超えている。まともな学者でない事こそが、まともの証しなのだ。
少なくとも全時代と地域を通してそれが圧倒的多数であり、日本人の「まとも」は中国では、トキかイリオモテヤマネコほどの希少性がある。従って何も知らないで関わるとひどい目に遭うのだが、こうした中華文明の神髄は、生存性の観点から、折り紙付きの保証がある。
有り体に言うなら、日本人的「まとも」でないから、驚天動地の騒乱にも天災にも耐えて、無慮数千年、中国人は生き残ってきたと言える。つまり生き残りたければ中国人の真似をするのが、一つの最適解だという事だ。そう思えば、これも面白いけしきではなかろうか。