孔子家語・原文
1
子路問於孔子曰:「賢君治國,所先者何?」孔子曰:「在於尊賢而賤不肖。」子路曰:「由聞晉中行氏尊賢而賤不肖矣,其亡何也?」孔子曰:「中行氏尊賢而不能用,賤不肖而不能去。賢者知其不用而怨之,不肖者知其必己賤而讎之。怨讎竝存於國,鄰敵搆兵於郊,中行氏雖欲無亡,豈可得乎?」
2
孔子閑處,喟然而歎曰:「嚮使銅鞮伯華無死,則天下其有定矣!」子路曰:「由願聞其人也。」子曰:「其幼也,敏而好學;其壯也,有勇而不屈;其老也,有道能下人。有此三者,以定天下也,何難乎哉?」子路曰:「幼而好學,壯而有勇,則可也;若夫有道下人,又誰下哉?」子曰:「由!不知。吾聞以眾攻寡,無不剋也;以貴下賤,無不得也。昔者周公居冢宰之尊,制天下之政,而猶下白屋之士,日見百七十人,斯豈以無道也,欲得士之用也,惡有有道而無下天下君子哉?」
孔子家語・書き下し
1
子路孔子於問いて曰く、「賢しき君の國を治むるに、先たる所の者は何ぞや」と。孔子曰く、「賢しきを尊び而肖不るを賤しむ於在り」と。子路曰く、「由聞くならく、晉の中行氏賢しきを尊び而肖不るを賤しみ矣と。其の亡ぶは何ぞ也」と。孔子曰く、「中行氏賢しきを尊び而用いる能わ不、肖不るを賤しみ而去る能わ不。賢しき者は其の用い不るを知り而之を怨み、肖不る者は其の己を賤しめるを必ずするを知り而之に讎す。怨み讎し竝びて國於存り、鄰の敵兵を郊於搆へば、中行氏亡ぶ無きを欲むと雖も、豈に得可き乎」と。
2
孔子閑に處りて、喟然と而て歎いて曰く、「嚮に銅鞮伯華を使て死ぬ無からば、則ち天下は其れ定まる有る矣らん」と。子路曰く、「由願わくば其の人を聞かん也」と。子曰く、「其れ幼き也、敏くし而學を好み、其れ壯んたる也、勇有り而屈ま不、其れ老いたる也、道有りて能く人に下れり。此の三者有らば、以て天下を定む也、何ぞ難からん乎哉」。子路曰く、「幼くし而學を好み、壯んにし而勇有らば、則ち可なる也。若し夫れ道有りて人に下らば、又た誰か下らん哉」と。子曰く、「由や知ら不。吾聞くならく、眾きを以いて寡きを攻めば、剋た不る無き也。貴きを以いて賤きに下らば、得不る無き也と。昔者周公冢宰之尊きに居りて、天下之政を制え、し而猶お白屋之士に下り、日に見ること百七十人、斯れ豈に道無きを以いん也。士を得るを之れ用いんと欲する也、惡んぞ道有り而天下の君子に下る無き有らん哉」と。
孔子家語・現代語訳
1
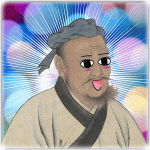

子路が孔子に質問した。「名君が国の政治を取るに当たって、真っ先にするのは何でしょう。」
孔子「賢者を尊び、馬鹿者をいやしむことだな。」
子路「私はこういう話を聞いています。晋の中行氏も、賢者を尊び、馬鹿者をいやしみました。なぜ滅んでしまったのでしょう。」
孔子「中行氏は賢者を尊びはしたが、官職を与える事が出来なかった。馬鹿者をいやしんだが、(官職から)追い払うことが出来なかった。賢者は中行氏が採用しないと知って怨み、馬鹿者は中行氏が必ずいやしむのを知って仕返しを謀った。
怨み屋と復讐者がどちらも国内に居て、しかも隣の敵は軍隊を送り都城のそばに陣を敷いた。中行氏が滅びたくないと願っても、どうしてかなうだろうか。」
2

孔子が暇を持て余してぼんやりしながら、ため息をついて言った。「むかしの銅鞮伯華が死ななかったら、あるいは天下の動乱は収まっていただろうな。」
子路「わたしは出来ますなら、その人について聞きたいです。」
孔子「幼いときにはキビキビと動いてよく学び、成人してからは勇気があってへこたれず、老いてからは道(行動の原則)を心得、人に頭を下げる事が出来た。この三つがあったら、それで天下の動乱を収めるのは、どうして難しいと言えようか。」
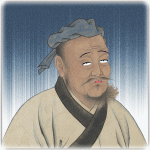
子路「幼いときによく学び、大人になってから勇気があるというのは、それは仰る通りでしょう。しかしそもそも、道を心得た人でさえ人に頭を下げねばならないなら、(道を心得ない世間の連中は、)いったい誰が頭を下げるでしょう。」
孔子「子路よ、お前は知らないのだ。私はこう聞いている。多勢が無勢を攻めれば必ず勝つ。高貴な者が下賎の者に頭を下げれば、必ずその心をつかむことが出来る、と。

むかし周公は宰相という高い地位にあり、天下の政治を握っていたが、粗末な家に住む痩せ浪人にも頭を下げ、一日に百七十人と会っていた。これを道を心得たとは言わんのか。人材を得たいと心から願っていたからだ。どうして道を心得ながら、天下の人材に頭を下げずにおられようか。」
孔子家語・訳注
1
中行氏:晋の門閥家老の一家。BC490、他の門閥家老家、すなわち智氏と、のちに晋を三分して独立する韓氏・魏氏・趙氏、四家の連合軍による袋だたきに遭って滅びた。
2
銅鞮伯華:孔子家語弟子行7にも登場した晋の名臣。生没年未詳だが、仕えた悼公の在位がBC573-BC558なので、孔子が生まれる十年前ほどの時代に活躍したことになる。孔子が生まれる前年(BC552)には、晋国内の政争に巻き込まれて収監されたという。
”あのお人が生きていればなあ”という孔子の発言から、もし本章が史実を伝えるとしたら、そのまま獄死したのではないか。
則天下其有定矣:ここでの「有」は、”あるいはそういうことがある”の意。
若夫有道下人,又誰下哉:元ネタである『説苑』尊賢篇では、「夫有道又誰下哉」(それ道あらば又た誰ぞ下らん哉)とあり、”そもそも道を心得たなら、誰が頭を下げるのでしょう”と素直に解せる。つまりそれほど偉い人が、どうして卑屈になる必要があろうか、ということ。
しかし本章では「下人」があることによって文意が通らない。
和刻本は「誰下哉言、誰下有道人乎」=”誰下哉とは、誰が原則を心得た人にへり下るのか、を言う”と注を付けている。「有道人」が腰を低くしており、一般人がそれに対して腰を低めると、いっそう「有道人」が低めるので、低くしようが無いと言うのだろうか。
「ドーゾドーゾ」「イエイエ」「イエイエドーゾ」。けしきを想像するといい。偽善者が集まってバカげた見せ物を繰り広げているとしか思えない。
結果として、「有道人」→「頭を下げる」が孔子の言明として、子路の理解は「非有道人」→「頭を下げない」と解した。逆・裏・対偶の関係が滅茶苦茶だが、中国に形式論理学が入るのは、清朝が滅びかかってからである。
周公:周王朝初期の摂政で王族の一人。魯の開祖でもある。
白屋:かやぶき屋根の家屋。粗末な家。庶民の家。
欲得士之用也:ここでの「之」は、「~をこれ…す」とよみ、「~を…する」と訳す。倒置・強調の意を示す。
孔子家語・付記
1・2共に、『説苑』尊賢篇のコピペ。